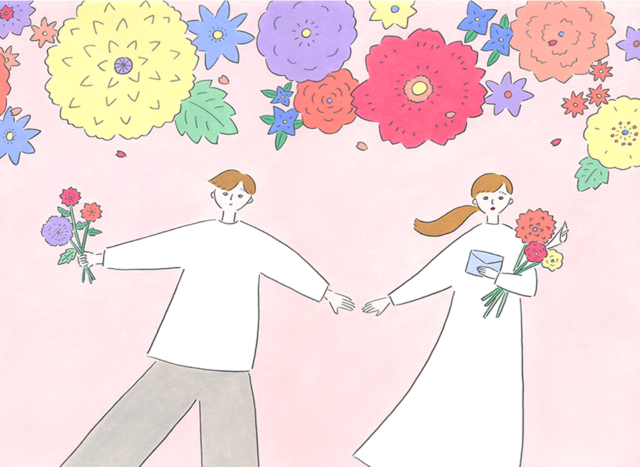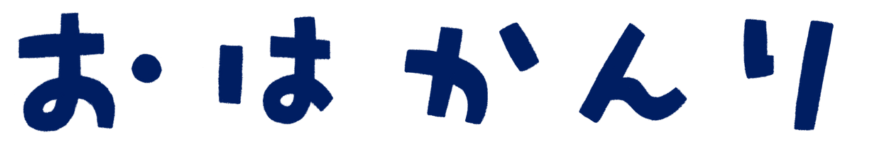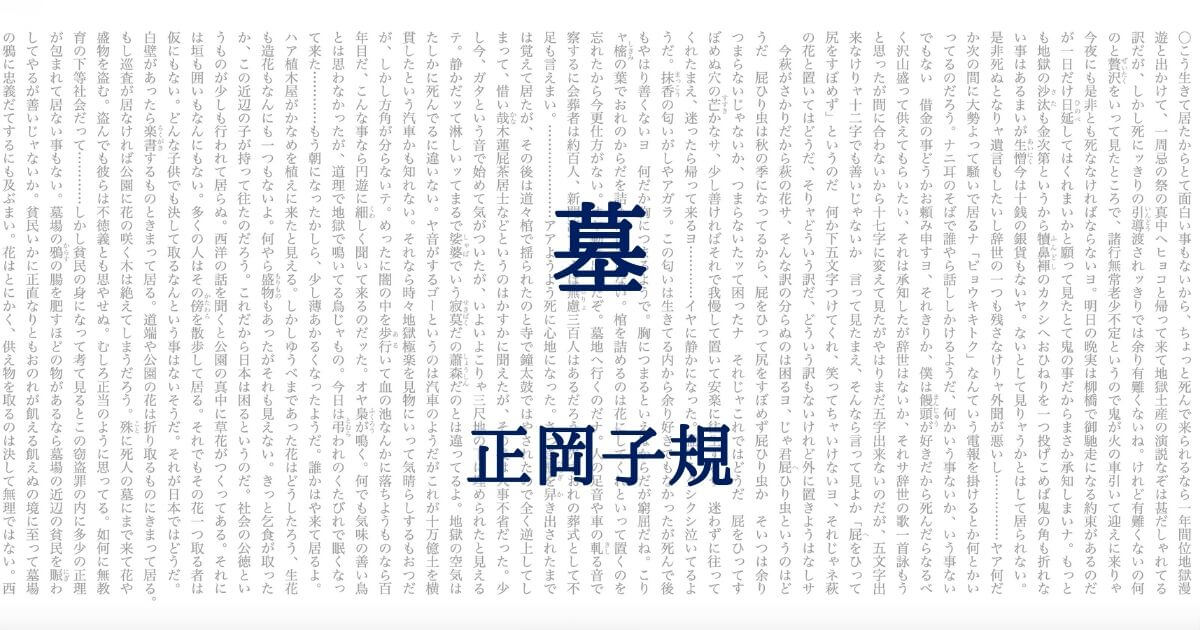「墓」というタイトルの短編があったので、読んでみました。作者はかの有名な俳人・正岡子規。
「死」を迎え「墓」に入るある男の、心の声がユーモア混じりに描かれるなかに、多くの気づきがあったので、ご紹介します。

120年以上も前の「墓」をテーマにした、随筆文に興味津々です。
「墓」の初出は、1899(明治32)年9月10日「ホトトギス 第二巻第十二号」とあります。短いのですぐ読めます。
実際には、オーディオブック
![]() に入っていたので、耳で聞きました。明治時代の散文なので読み慣れていないのもありますが、一人称で語られる文体なので、耳読ならすーっと入ってきておすすめです。
に入っていたので、耳で聞きました。明治時代の散文なので読み慣れていないのもありますが、一人称で語られる文体なので、耳読ならすーっと入ってきておすすめです。
「墓」のあらすじ
主人公の語り部が、死ぬところからはじまります。
死んでからは、斜め上からこの世を見ているような描写となります。自身の墓ができて葬られるまで。そしてその墓での出来事が時折り語られ、都度思いを吐露していきます。
本人は地獄にいるという設定なのですが、その割にはユーモア混じりにこの世を見物しているようです。
故人となったからなのか、家族や人を思う気持ちに素直になり、幸せを願っていることや、一方で葬られてからの寒さや寂しさを感じていることなども語られます。
時は流れ、ついには墓に誰も来なくなるというところまで……忘れられていく悲哀、薄情な人の性を憂いているのかいないのか。
決して暗く落ち込むわけではなく、そんなもんだよね、と風刺をきかせながら悟ってもいる。そんなお話です。
現場からの定点観測レポート
この語り部、死ぬ以前の段階から、魂は肉体の外にあって、身の回りの世界を俯瞰的に見ているようです。
でも土葬されてからは、その魂はお墓の場所にあるのです。まるであの世とこの世が通じる場所が、お墓しかないように描かれています。
だから、お墓の現場からしか世の中の動きを知ることができません。だから、人が来るを待っているのです。
時が経つにつれ、お墓からのレポートの間隔は空いていきます。誰も来ないから。
書かれたのは120年も前なのに、現代人こそが身につまされる「わかる」感覚。
墓に対する日本人の墓との関わり合いや感性は、意外にも変わっていないのか、正岡子規の先見の明が刺さるのか。
ときに「墓」を訪れる人に世の中をみる視点の鋭さに驚きながらも、「墓」が世をうつす鏡のようにも思えたのでした。
背景を知るとより切ない
正岡子規はこれを書いたのは32才、それから約2年後に亡くなっています。書いた当時はもう自由に歩くことはできなかったそうです。不治の病であった結核を長く患い、死と隣り合わせにあった境遇は慮るしかありませんが、単なる社会風刺でないことは明らかでしょう。
自身の先行きを案じない訳がありません。遺稿がどうなるのかの心配をしているくだりもあるのですが、やはり子規自身がそのまま重なります。
死んでしまってはもうどうしようもない、あとの人に任せるしかない、諦める訳でもなく独り言つしかないのが「死」であるのです。「墓」は正岡子規の、遺言書の一部であり、その草稿のようにも思えます。
散文の終わり、自著のあとに、子規自身の墓に対する願いが、数行記されています。
僕が死んだら道端か原の真中に葬って土饅頭を築いて野茨を植えてもらいたい。
正岡 子規「墓」跋文より
(中略)石を建てても碑文だの碑銘だのいうのは全く御免蒙りたい。
実際のお墓は、東京都北区の大龍寺にあるそうで、空襲で焼けてしまっているとはいえ、大切に弔われているようです。
はたして本人の意向が反映された墓なのかどうか、この短編を読んだだけでは知ることはできません。でも、誰もが思いを馳せてみる場所があることに安心します。
正岡子規の作品の多くは青空文庫で読むことができます。ありがたいかぎりです。
時代を経てもある部分では通じる「墓」の姿に驚かされ、示唆に富んでいて、自身には何を問われるか、考えさられる出会いでした。エンタメとしても純粋に面白いですよ。